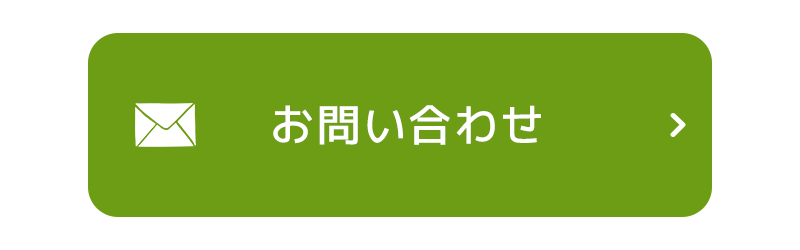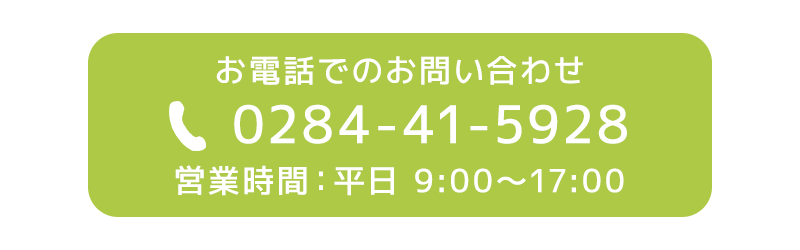相続税の対策について

円満な相続のためには事前準備が必要不可欠です。
現状の財産をきちんと把握したうえで、生前贈与は必要なのか、必要な場合、いつ、いくらくらい贈与すればよいのかといったシミュレーションを行います。
■サービス内容
- 財産分析
- 相続税シミュレーション
- 生前贈与
- 生命保険等の活用
相続発生前の準備
相続が争族にならないために!
何事も事前に準備しておくことが大切です。
当事務所では相続前の準備段階から相続発生時・相続後のご相談まで、お手伝いさせて頂きます。
| 相続財産の調査 |
▼
相続の対象となる財産の調査・確定作業を行います。調査の結果は、財産目録の作成により完了します。
「どの財産が、どれだけあるのか」ということが誰が見ても分かるように財産目録を作成することが重要です。
| 相続人の調査 |
▼
相続人(法定相続人)は誰なのかを調査します。 戸籍の収集等により、相続人に漏れがないようなリストを作成しておくことが好ましいでしょう。
司法書士などの専門家に依頼して相続人リストを作成すると、正確性が担保されます。
| 節税対策 |
▼
相続財産と相続人の調査・確定作業が終了したら節税対策に取り組みます。節税の方法としては財産評価を下げる方法や生前贈与等があります。
| 遺言書の作成 |
相続が争族にならないように遺言書を生前にきちんと準備しておく事も重要となります。
遺言書

遺言には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。後々のトラブルを最小限にするためには「公正証書遺言」をおすすめします。
なお、2019年1月13日より施行されている民法(相続関係)改正法において、自筆証書遺言の方式が緩和されました。詳しくは「法律等の改正」の内容をご確認ください。
| 自筆証書遺言 |
公正証書遺言 | |
| 作成方法 |
遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容などの全文を自書し、押印して作成 ただし添付する財産目録については、各頁に署名・押印すれば自書でなくても良い (パソコン・ワープロでの作成、通帳のコピー、不動産の登記事項証明書等でも可) |
遺言者が、原則として証人2人以上とともに公証人役場に出かけ、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成 |
| メリット |
|
|
| デメリット |
|
|
その他相続情報

相続対策には以下のようなものがあります。
生前贈与を利用して財産を減らす
暦年課税による贈与、配偶者への居住用財産の贈与、相続時精算課税制度の利用、一代飛び越し贈与などです。
所有財産の相続税評価額を下げる
不動産の有効活用、土地の利用形態の変更、預貯金から減価財産(家屋等の取得)への組替えなどです。
無理のない借金を作る
資金繰りには十分に検討し、遺産を分割しやすくする。
納税資金対策
事業用土地の収益性の向上、生命保険の活用、物納財産の確保などです。
遺言書の作成
相続の方針を明確にし、争いを防ぐため、遺産の分け方や遺言執行者を記載した遺言書を作成しておきます。
ご相談の流れ

ご面談
初回のご面談でお客様のご要望をお伺いします。また、相続税や贈与税の概要をご説明します。

料金のご提示
ご依頼いただく内容を確認し、料金のお見積額をご提示いたします。

詳細分析・対策プランのご提案
財産を詳細に分析し、相続税のシミュレーションを行った後、生前贈与・生命保険の活用など、最適な節税・円滑な承継のためのプランをご提案いたします。
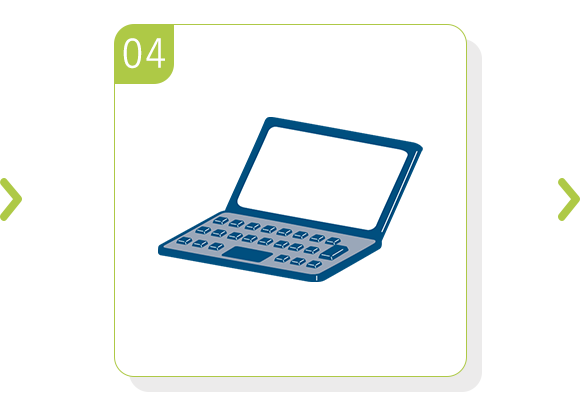
対策の実行・相続発生前の準備
ご提案したプランに沿って、お客様ご自身で贈与や財産整理などの対策を進めていただきます。当事務所では、その過程でのご相談対応や必要な手続きのサポートを行い、安心して準備を進められるようお手伝いいたします。

アフターフォロー・相続発生時の対応
相続発生後の相続税申告などの手続きも、引き続き当事務所がお手伝いいたします。
相続前から相続後まで、一貫した安心のサポート体制をご提供いたします。