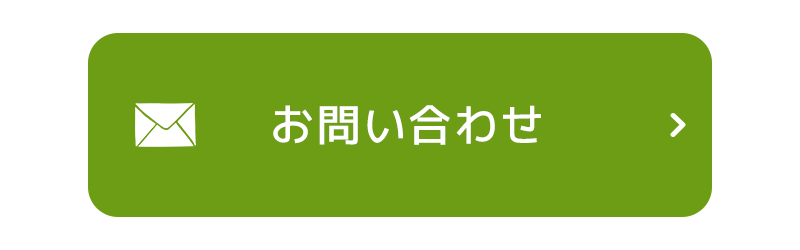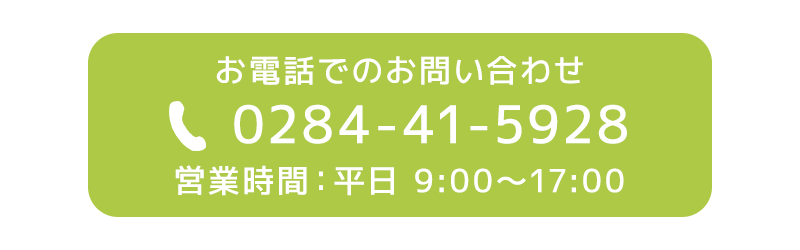相続税の申告が必要な方

相続は突然発生する可能性もあります。まずはお気軽にご相談ください。
節税対策から相続税申告まで、お客様に寄り添いながらご支援させていただきます。
当事務所では相続が「争族」とならないよう専門家として丁寧な対応を行って参ります。
諸手続き
手続きすることによりもらえるもの、引き継ぐもの、解約するものなどさまざまな手続きがあります。また必要な書類も手続き先も多種多様です。
知らないと損をすることがありますよ!
例1: 国民健康保険の加入者が亡くなった場合は葬祭費として3万円~7万円(市町村によって異なります)が受け取れます。
例2: 社会保険の加入者が亡くなった場合は埋葬料として5万円が受け取れます。
※いずれも申告制ですので手続きをしないと受給できません。加入者が亡くなった日から2年以内に申請しなければ権利がなくなりますので注意が必要です。
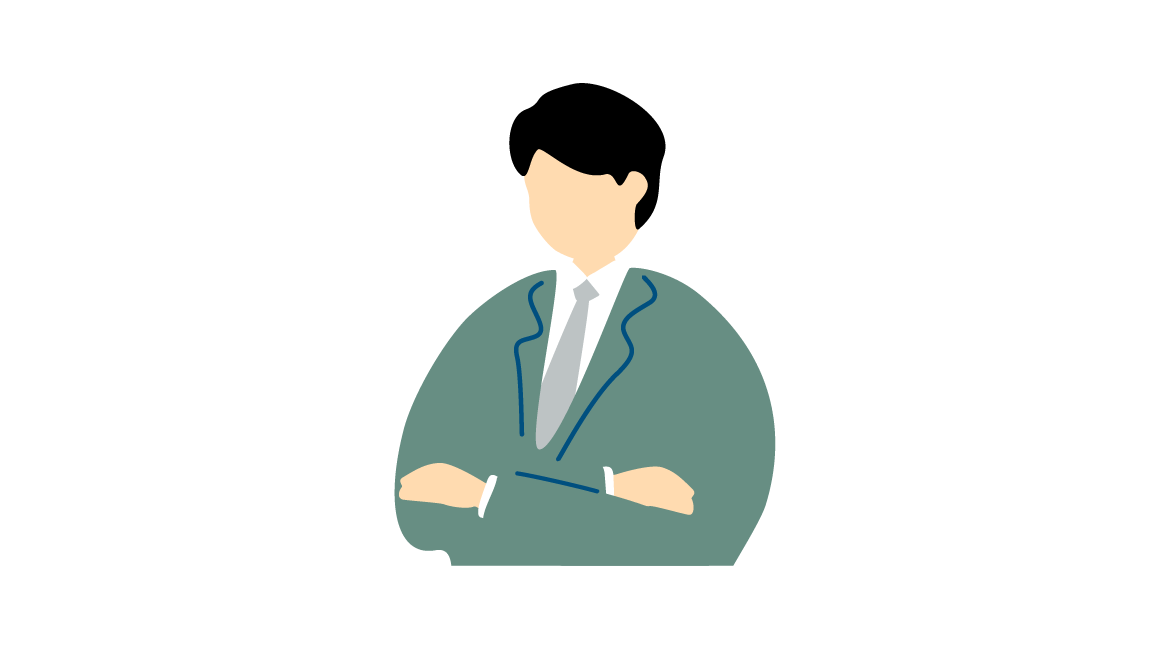
請求
・生命、簡易保険請求手続き
・高額医療費の受給手続き
・葬祭費の請求
・埋葬料の請求
・住宅ローン(団信)手続き
・預貯金の引出しと手続き
・遺族年金
届出
・死亡届
・火葬許可申請書の提出
・世帯主変更届
・児童扶養手当認定請求書
・復氏届
・婚姻関係終了届
・準確定申告
・運転免許証の返納
・シルバーパス等の返納
・パスポートの返納
・年金の支給停止届
変更または解約
・不動産登記
・自動車保険
・家屋の火災保険
・公共料金
・NHK
・自動車の所有権移転手続き
・電話加入権の継承
・株券・債券の名義変更
・クレジットカードの解約届
・インターネット等の解約届
遺留分
民法では、被相続人の自由な財産処分を認めながらも、遺言によっても侵害できない一定の割合を定めています。
遺留分とは、この一定の割合のことで、不当な遺言をされた相続人を救済するものです。
| 相続人 | 遺留分 |
|---|---|
| 配偶者のみ | 1/2 |
| 子のみ | 子全員で1/2 |
| 直系尊属のみ | 直系尊属全員で1/3 |
| 配偶者と子 |
|
| 配偶者と直系尊属 |
|
| 配偶者と兄弟姉妹 |
|
遺留分の侵害があっても、その事実だけでは生前贈与や遺言等が無効になるわけではありません。遺留分を侵害された相続人が侵害を受けた部分を取り戻すためには、遺留分の侵害額の請求をすることが必要です。
2019年7月1日より施行されている民法(相続関係)改正法(以下、改正法)では、遺留分侵害額の請求権の行使により生ずる権利が金銭債権となりました。これにより従来当然に生じていた共有関係を回避し、遺言者の意思を尊重する事ができるようになりました。
※遺留分については、この他にも改正された点があります。詳しくは「法律等の改正」の内容をご確認下さい。
なお、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った日から1年を経過した場合には、遺留分侵害額請求権は消滅し(時効)、相続開始から10年を経過した場合にも(相続の開始等の事実を知らなくても)、遺留分侵害額請求権は消滅します。
せっかく遺言書を作っても、遺留分を侵害していると、相続争いのタネになる場合もあります。遺留分に十分注意を払い、遺産を特定することが大事です。
遺産の分割方法によっては、相続税が減少するケース(配偶者の税額の軽減の活用など)もありますので、2次相続を考慮して将来を見据えた分割を考えることが大切です。
※2次相続とは、相続した相続人が亡くなって被相続人になったときの相続をいいます。
ご相談の流れ

ご面談
相続税の対象となる財産は何か、初回のご面談でお伺いし、ご説明をいたします。その上で相続税の概算額をお伝えいたします。

料金のご提示
初回のご面談時にご依頼いただく内容を確認し、料金のお見積額をご提示いたします。

財産目録の作成
財産目録を作成し、お客様に遺産分割の方針をヒアリングいたします。また、適正な財産評価により、税金を過剰に納めることを防ぎます。
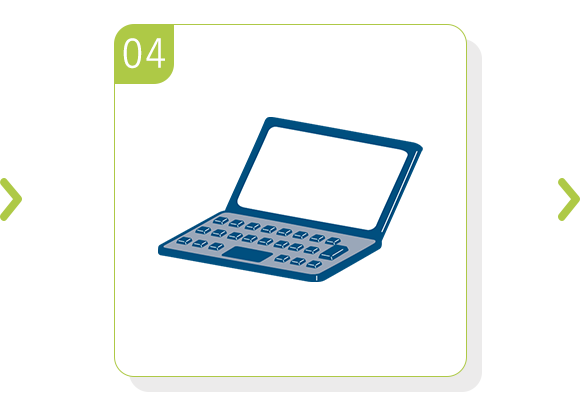
相続税申告書の作成
お客様の遺産分割方針に基づき遺産分割協議書を作成いたします。また、遺産分割に基づく相続税申告書も作成します。

アフターフォロー
税務調査の立会、交渉など、税務代理に基づき対応します。相続をされた不動産の有効活用や処分など、豊富な経験に基づき相談に応じます。